2019.2.20 (水) あの犬は良い犬だった
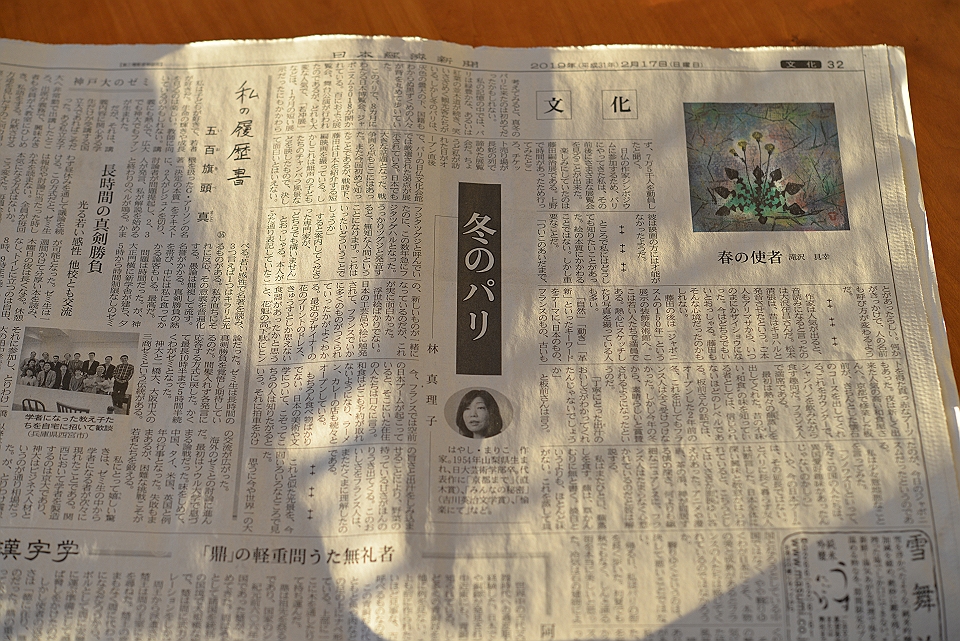 4分の1に折りたたまれた新聞が、食器棚に無造作に置かれている。「はやく1階の資源ゴミ置き場に持っていかなければ」と考えつつ手に取ると、それはさきおとといの日本経済新聞だった。ウチは週のうち日曜日がもっとも忙しいから、ベランダの籐椅子でコーヒーを飲みつつ日曜版の新聞を寛いで読む、というような優雅な時は持てない。そして結局のところ、日曜日の新聞はほとんど読まない。
4分の1に折りたたまれた新聞が、食器棚に無造作に置かれている。「はやく1階の資源ゴミ置き場に持っていかなければ」と考えつつ手に取ると、それはさきおとといの日本経済新聞だった。ウチは週のうち日曜日がもっとも忙しいから、ベランダの籐椅子でコーヒーを飲みつつ日曜版の新聞を寛いで読む、というような優雅な時は持てない。そして結局のところ、日曜日の新聞はほとんど読まない。
4分の1に折りたたまれたその新聞を何気なく2分の1まで開き、そこから更に開くと、もっとも後ろの紙面つまり第32面の真ん中に「冬のパリ」という活字が見え、その瞬間、”AGFDC”となだらかに落ちる旋律が聞こえたような気がした。言うまでもなく”Autumn in New York”の出だしの部分である。そんなことを書きながら、秋、どころかそもそもニューヨークという街に僕は行ったことがない。しかし冬のパリなら知っている。
1979年のいまだ松の内、成田空港からエアフランス機に乗った。シャルルドゴール空港とオルリー空港とのあいだをどのようにして移動したかの記憶は無い。当時、日本とスペインのあいだに直行便は飛んでいなかった。「行き先はマラガですね」と僕のスーツケースにチョークを走らせようとした職員に「違う、マドリッド」と慌てて答えたことは覚えている。当時、空港のベルトコンベアが荷物に貼られたバーコードを光電管で読み取る仕組みは無かった。
マドリッドは暖かく、グラナダは更に暖かかった。帰りはパリで数日を過ごした。朝、ちかくの公園を歩きながら「こんなところで冷たい空気を吸い続けたら、呼吸器がおかしくなるに違いない」と、紳士の連れた人なつこい犬の頭を撫でると即、ホテルへときびすを返した。
「冬のパリ」を書いた林真理子は、現地で蕪蒸しを食べたという。僕はパンと生牡蠣と鶏のワイン煮を食べ、カフェオレとワインを飲んだ。パリまで足を延ばすことは、もうないと思う。
朝飯 豆腐と菜花と若布の味噌汁
昼飯 「金谷ホテルベーカリー」の2種のパン、コーヒー
晩飯 大根と胡瓜と林檎のサラダ、“Signifiant Signifie”の3種のパン、2種の温野菜を添えた豚肉とソーセージのソテー、“Petit Chablis Billaud Simon 2015”、チーズのブリオッシュ、”Old Parr”(生)













